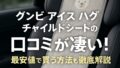「どの知育雑誌を選べばいいの?」と迷っていませんか?
この記事では、人気の知育系雑誌を年齢別に徹底比較し、それぞれの特徴や選び方、注意点、そして効果的な併用法まで詳しくまとめました。
こどもの発達に合った雑誌を選ぶことで、自然と学ぶ力が育ち、親子の時間ももっと楽しくなります。
目的別のおすすめや、失敗しないためのポイントもご紹介しているので、初めての方でも安心です。
最後まで読めば、あなたのご家庭にぴったりな知育雑誌がきっと見つかりますよ!
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
注:ドコモガラケーF503i 付録は電子版には含まれません
知育系雑誌おすすめ12選を年齢別に比較
知育系雑誌おすすめ12選を年齢別に比較して紹介します。
それぞれの年齢層ごとに、人気の知育雑誌を紹介していきますね。
①0歳~2歳向けの人気知育雑誌
0~2歳向けの知育雑誌は、「五感を刺激する」ことがポイントです。
この時期は、目で見て楽しい、音が出る、触って遊べるなど、遊び感覚で自然と学べる工夫がされているものが多いです。
代表的な雑誌には、『ベビーブック』(小学館)や『こどもちゃれんじbaby』(ベネッセ)があります。
特に『こどもちゃれんじbaby』は、成長段階に合わせた絵本・音楽・知育おもちゃが毎月届き、親も育児のヒントが得られると人気なんです。
我が家でも使ってましたが、しまじろうが出てくるだけで笑顔になってくれるので、本当に助かりましたよ〜!
②3歳~4歳向けのおすすめ雑誌
3歳〜4歳になると、「自分で考える」「話す」「体を使う」といった力が伸びる時期です。
この年代におすすめなのは『おともだち』『げんき』『いないいないばぁっ!』などのキャラクター系知育雑誌。
また、通信教材と連動している『こどもちゃれんじぽけっと』『ぷち』なども人気ですね。
絵本やシール、工作、迷路などの遊びの中に、「数感覚」や「ひらがなへの興味づけ」などが自然と盛り込まれていて、子どもが飽きにくいんです。
うちの子も迷路やシール遊びが大好きで、「次いつ届くの?」と楽しみにしていました♪
③5歳~6歳向けの高評価雑誌
就学前の5歳〜6歳では、「学ぶ」姿勢がぐっと育つ大切なタイミングです。
この時期にぴったりなのが、『幼稚園』 『キンダーブック』『がくしゅうおおぞら』といった雑誌。
特にZ会の「かんがえるちからワーク」などは、論理的思考力を養いたい家庭から注目を集めています。
また、『こどもちゃれんじ すてっぷ』は、ひらがな・かず・時計・人間関係・プログラミング的思考まで網羅していて、かなり本格的。
遊びだけでなく、就学準備を意識するならこの年代から意識して選んであげると安心ですよ〜!
④小学生向けの知的好奇心を育てる雑誌
小学生になると、読み物や実験系、社会とのつながりを意識した雑誌がおすすめです。
『子供の科学』『たくさんのふしぎ』『小学一年生』などが定番ですね。
また、学年に応じて『科学と学習』『最レベ問題集』などの教材系雑誌を取り入れる家庭も増えています。
子どもの興味を引き出しながら、学びに変えていける編集がされていて、大人も一緒に楽しめる内容です。
理科や実験が好きな子には「付録のキット付き雑誌」もヒットしますよ!
⑤特別支援が必要なお子さん向けの雑誌
発達に特性のあるお子さん向けには、『チャレンジタッチ』や『トモエそだち』など、個別のペースで学べる雑誌・教材が注目されています。
「聴覚・視覚優位」などの学習スタイルに合わせた内容設計や、ステップごとの学びができる紙媒体・タブレット両対応の教材があるのが特長。
教材そのものだけでなく、「親子でどう向き合っていくか」がテーマになっているのも特徴的です。
選び方に迷ったら、必ず公式サイトや相談窓口が用意されている雑誌を選ぶと安心ですよ。
うちの甥っ子も発達グレーでしたが、そういった雑誌のおかげで前向きに学べるようになっていきました!
知育雑誌を選ぶときの4つのポイント
知育雑誌を選ぶときの4つのポイントを紹介します。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう〜!
①対象年齢と発達段階の合致
まず大切なのは「対象年齢」が、わが子の発達に合っているかどうかです。
たとえば、3歳児でもひらがなに興味が強い子もいれば、まだお絵描きがメインの子もいますよね。
雑誌の対象年齢はあくまで目安なので、実際の中身を見て、子どもの発達段階に合っているかをチェックするのが大事なんです。
年齢より少し下の内容でも「できた!」という達成感を得られると、学ぶ意欲が育ちますし、逆にレベルが高すぎるとやる気を失ってしまうので要注意。
「今、ちょうどちょっと頑張ればできる内容」がベストですよ〜!
②付録・教材のクオリティ
知育雑誌の魅力のひとつは、やっぱり「付録」ですよね。
子どもは目新しいものにとても敏感なので、付録のおもちゃや教材のクオリティが高いと、自然と興味を持ってくれます。
とはいえ、付録目当てで選ぶと「一回遊んで終わり…」なんてこともあるので、教材としっかり連動しているものを選ぶのがポイント。
例えば『こどもちゃれんじ』は、知育玩具・絵本・ワークが三位一体になっていて、付録も遊びながら学べる仕掛けが満載。
「楽しい=学びになる」設計がされているか、ぜひチェックしてみてくださいね♪
③継続しやすい価格帯
知育雑誌は一回買って終わりというより、「継続」が大事です。
そのため、無理なく続けられる価格かどうかはかなり重要なポイント。
月刊タイプの知育雑誌なら、だいたい1,000円〜2,000円台が相場ですが、付録の豪華さやボリュームによって価格差もあります。
安すぎると内容が物足りないこともありますし、高すぎても続かない…というジレンマ、わかりますよね。
まずはお試しで1号だけ買ってみて、「このくらいのボリュームと値段なら続けられそう」というバランスを見極めるのがオススメです!
④親も一緒に楽しめる内容かどうか
実はここ、めちゃくちゃ大事です!
知育雑誌は「親子で一緒に使う」ことが前提になっているものが多いです。
だからこそ、親が一緒に楽しめるか、学べるか、ってすごく大事なんですよ。
たとえば『こどもちゃれんじ』では育児アドバイスや発達に関するコラムもついていて、「これ、今のうちの子にぴったり!」という発見があります。
親子で取り組む時間が「知育=楽しい」に変わると、子どももどんどん吸収していくので、親のモチベーションも一緒に上がる構成になっているか、見てみてくださいね!
定期購読できる知育雑誌とそのメリット5つ

定期購読できる知育雑誌とそのメリットを5つに分けて解説します。
「買いに行く手間なし」で便利なうえ、定期購読ならではの嬉しい点がたくさんありますよ〜!
①毎月届くワクワク感が学習習慣に
定期購読最大のメリット、それは「毎月、楽しみに待つ習慣がつく」ことです。
子どもにとって“自分宛てに届く荷物”って、特別な体験なんですよね。
「今月はどんな付録かな?」「新しいワークはどんなのかな?」とワクワクしながら待つことで、学習そのものがイベント化されていきます。
それによって「届いたら机に向かう」「遊びながら学ぶ」という流れが自然と身につきやすくなるんです。
親が声かけしなくても、自分から取り組んでくれるようになるって嬉しいですよね♪
②教育的なカリキュラムで安心
知育雑誌の多くは、年齢に応じたカリキュラムがしっかりと構成されています。
特にベネッセやZ会など大手出版社が提供しているものは、教育心理学や発達段階をベースに設計されていて、安心して使える内容です。
「この時期はこういうテーマで学ぶといい」というノウハウが詰まっていて、素人ではなかなか難しい“育児と教育のプロ視点”が得られるのが強み。
子どもにとっても無理なく学べる流れになっているので、挫折しにくいですよ!
やっぱりプロが考えてるカリキュラムって、スムーズさが違いますね〜。
③おもちゃの代わりに知育玩具が届く
毎月の知育雑誌には、教材だけでなく「付録」として知育玩具がついてくることが多いです。
この付録、実は“おもちゃ代わり”になるくらい子どもがハマる工夫がされてるんですよ。
市販のおもちゃと違って、「学びにつながる仕掛け」が詰まっているので、遊んでるうちにひらがなや数、社会ルールなどが身についていきます。
うちは「これがあるなら他のおもちゃ買わなくていいかも」と思うこともしばしば…(笑)
結果的にコスパも良くなりますし、親としてもありがたいですよね!
④情報誌として親の学びにもつながる
意外と見落とされがちなのが、「親向けコンテンツの充実度」です。
『こどもちゃれんじ』のような雑誌には、育児のアドバイスや発達段階に関する読み物もセットになっていることが多く、「今どんな声かけが効果的か」「生活習慣の身につけ方」などの情報が得られます。
これがほんと助かるんですよ…!
育児書を読む時間がなくても、雑誌でサクッと知識が得られるって最高です。
「今月のテーマ」みたいな特集もあって、まるで自分の育児をガイドしてくれるかのような心強さがあります♪
⑤子どもの興味に沿って継続しやすい
子どもって、「今これにハマってる!」って時期がありますよね。
定期購読の知育雑誌は、そういった子どもの“今”の興味に寄り添える内容になっていて、興味が薄れる前に「次」が届くことでモチベーションをキープしやすいんです。
また、成長に合わせてレベルアップしていく仕組みになっているので、無理なくステップアップできます。
続ければ続けるほど、子ども自身も「できることが増えた!」という実感が湧くので、自信につながりますよ!
「継続は力なり」って、ほんとにその通りですね〜!
知育雑誌のデメリット・注意点も知っておこう
知育雑誌のデメリット・注意点も知っておきましょう。
知育雑誌ってすごく魅力的なんですが、ちゃんと「向き・不向き」もあるんですよね。
①付録が多く物が増えやすい
知育雑誌の魅力でもある「付録」、これは裏を返せば「物が増える」原因にもなります。
毎月届くと、一年で12個以上の知育おもちゃや小物が増えるわけで、正直…収納が追いつかないこともあります。
「最初は遊んだけど、そのあとは放置」なんてケースもあるあるなんですよね。
我が家では“使わなくなった付録は一時ボックスにまとめて、2ヶ月後も遊ばなければ処分”というルールを作って乗り越えてます。
継続するなら「収納スペースの確保」や「定期的な見直し」もセットで考えるとストレスが減りますよ〜!
②子どもが飽きることもある
「子どもが楽しめる内容」というのが売りの知育雑誌ですが、すべての子どもにピッタリ合うとは限りません。
興味の波ってほんとに早くて、「先月はめっちゃハマってたのに、今月は全然…」なんてことも普通にあります。
特に“学び要素が強め”だと、「お勉強みたいでイヤ!」と感じる子も。
そういう場合は、無理にやらせずに一度お休みする、別の雑誌に切り替えるなどして、「楽しい」を第一に考えてあげるといいですよ。
親の「せっかく買ったのに…」って気持ちも分かりますけどね、グッとこらえましょう(笑)
③お試しできない雑誌も多い
意外と多いのが「中身が見えない状態で申し込みが必要」な雑誌。
定期購読が前提の雑誌や、オンライン専売の雑誌だと、事前に試し読みができなかったり、現物を手に取って確認することができないケースもあります。
その結果、「思ったのと違った…」「子どもが興味を持たなかった…」といった後悔につながることも。
できれば事前に“口コミ”や“レビュー動画”、“過去のバックナンバー画像”を見ておくと、ミスマッチが減らせます。
気軽に始められるのが魅力ですが、「失敗しない工夫」も忘れずに!
④似た内容が重複しやすい
知育雑誌はテーマが月齢・年齢ごとに構成されているため、同じジャンルの雑誌を複数購読していると「内容がかぶる」ことがあります。
たとえば、「時計の読み方」や「ひらがなの練習」などは、ほとんどの雑誌で扱われる定番テーマなので、被ってしまうのは避けられないんですよね。
そうなると「また同じ内容か…」と子どもが飽きる原因になってしまうことも。
複数の雑誌を併用する場合は、「A誌は自然科学メイン、B誌は生活習慣メイン」など、テーマがかぶらないように選ぶといいですよ!
内容の重複をうまく避けて、バランスよく活用してくださいね〜。
知育雑誌×通信教材で効果倍増!おすすめ併用術
知育雑誌×通信教材で効果倍増!おすすめ併用術を紹介します。
単体でも魅力的な知育雑誌ですが、通信教材と併用することで「学びの幅」と「深さ」がぐっと広がりますよ〜!
①ポピーやこどもちゃれんじとの併用が人気
まずは王道の併用パターンをご紹介。
『ポピー』や『こどもちゃれんじ』は、知育雑誌としても通信教材としても人気ですが、実は“知育雑誌との併用”でも相性バッチリなんです。
たとえば『幼児ポピー』はシンプル構成で「書く・考える」系の教材が中心なので、キャラクターや付録の多い知育雑誌と組み合わせることで、遊びと学習のバランスが整います。
『こどもちゃれんじ』は教材が届くだけでなく、親向けの育児情報も充実しているので、全体の学習設計のベースとして活用できます。
雑誌は“今の関心”に応え、通信教材は“体系的な学び”を支えるという住み分けがうまくいくと最強の組み合わせに!
②タブレット学習と紙媒体を使い分ける
最近は『スマイルゼミ』や『Z会幼児コース』など、タブレット型の通信教材も増えてきました。
これに紙の知育雑誌をプラスすると、視覚・触覚・思考のバランスがとれて効果倍増です!
タブレットでは動画やアニメーションで直感的に理解でき、紙媒体の雑誌では“自分の手を動かして学ぶ”経験が積めるんですね。
この「デジタル×アナログ」の相乗効果が、脳への刺激をより多様にしてくれるんです。
我が家でも「今日はスマイルゼミ、明日は雑誌の工作」みたいにローテーションしてますよ♪
③知育本・絵本との組み合わせも◎
知育雑誌だけではカバーしきれない部分を、絵本や知育本でフォローするのもおすすめです。
例えば、雑誌で“時計の読み方”をやったら、翌週は“時計の絵本”を読み聞かせして理解を深める、というような流れですね。
「雑誌→実践→絵本で補強」みたいな形にすると、記憶の定着も良くなりますし、何より親子の会話が増えるんです!
関連する図鑑や絵本も一緒に使うと、知識の広がり方がぜんぜん違いますよ〜。
本屋さんで雑誌と一緒に絵本コーナーも覗いてみてくださいね♪
④雑誌付録を活かした遊び方アイデア
せっかくの雑誌付録、ただ使って終わりじゃもったいない!
実は、他の教材と組み合わせることで“遊びながら学ぶ力”がさらにアップします。
たとえば、ひらがな表の付録がついてきたら、それを壁に貼って「今日は“あ”のつくもの探し!」といったゲームを作る。
工作付録があれば、テーマに合わせて「お店屋さんごっこ」「バスごっこ」など、ロールプレイに発展させていく。
こうやって“自由な発展”を加えることで、雑誌の内容が「点」ではなく「線」になっていくんです。
学びは一方通行じゃなくて、いろんな体験とつながってこそ生きてきますよ!
迷ったらコレ!目的別おすすめ知育雑誌早見表
迷ったらコレ!目的別おすすめ知育雑誌早見表を紹介します。
選び方に迷ったときは、“目的別”に雑誌を選ぶとハズレにくいですよ〜!
①「学習習慣をつけたい」なら?
「自分から机に向かってほしい」「毎日ちょっとずつでも学んでほしい」そんな願いがある方には、
特に『こどもちゃれんじ すてっぷ』は、ワークとおもちゃ、絵本が一体化していて、遊びながら自然と学ぶ習慣が身につきます。
うちの子も「しまじろう届いた〜!」って、自分から教材を出して机に向かう姿には感動しました…!
②「英語も一緒に学びたい」なら?
「将来に向けて英語もやらせたい…」という家庭にぴったりなのが、
『こどもちゃれんじEnglish』や『Worldwide Kids』などの英語特化型の知育教材です。
『こどもちゃれんじEnglish』は、年齢に合わせた英語の歌・絵本・DVDが届いて、「英語=楽しい!」と感じさせてくれる構成が秀逸。
無理なく英語の音に触れられて、しかも日常会話や生活習慣とリンクしてるから、覚えるのが早いんですよね。
「英語に対する苦手意識をつけたくない」って人に、本当におすすめです!
③「生活習慣を身につけたい」なら?
歯みがき・トイレ・あいさつ・お片付けなど、「生活習慣を楽しく教えたい!」という人には、
『げんき』や『おともだち』、そして王道の『こどもちゃれんじbaby~ぷち』の各コースが強い味方!
しまじろうをはじめとしたキャラクターの力って、やっぱりすごいんです。
「しまじろうが歯みがきしてるよ!」と言うだけで、自分から磨き出すっていう…もう魔法かよって思います(笑)
実際に保育士さんや療育でも使われてる内容なので、安心して使えますよ♪
④「親子で楽しみたい」なら?
「せっかくなら親子で楽しみたい!」「子どもの反応を見ながら一緒に学びたい」という人には、
『たくさんのふしぎ(福音館書店)』や『かがくのとも』のような読み聞かせ中心の知的雑誌がおすすめ。
1冊で科学・社会・文学のエッセンスがぎゅっと詰まっていて、大人も「へえ〜!」と声が出る内容ばかりです。
実際、うちでも“寝る前に読んで一緒に感想を話す時間”がすごく良い親子タイムになってます。
知的な対話のきっかけになるので、ゆっくり関わりたいご家庭にはぴったりですよ!
まとめ|知育系雑誌まとめ記事でわかる年齢別の選び方
| 目的別おすすめ知育雑誌 | リンク |
|---|---|
| 学習習慣をつけたい | ①「学習習慣をつけたい」なら? |
| 英語も一緒に学びたい | ②「英語も一緒に学びたい」なら? |
| 生活習慣を身につけたい | ③「生活習慣を身につけたい」なら? |
| 親子で楽しみたい | ④「親子で楽しみたい」なら? |
知育系雑誌は、子どもにとって「楽しく学ぶ」きっかけになる優秀な教材です。
でも、それぞれに向き・不向きがあるので、年齢や発達段階、家庭の教育方針に合わせて選ぶことが大切です。
毎月届くワクワク感や、通信教材との併用による相乗効果、親子での関わり方など、雑誌の使い方次第で育ち方にも大きな違いが生まれます。
この記事では、読者のニーズに合わせて目的別・年齢別に雑誌を整理し、どんな家庭にも役立つヒントを詰め込みました。
知育雑誌は、“学びのきっかけ”としても、“親子のコミュニケーションツール”としても最適です。
一冊一冊の特性を理解して、ぴったりなものを見つけてあげてくださいね。